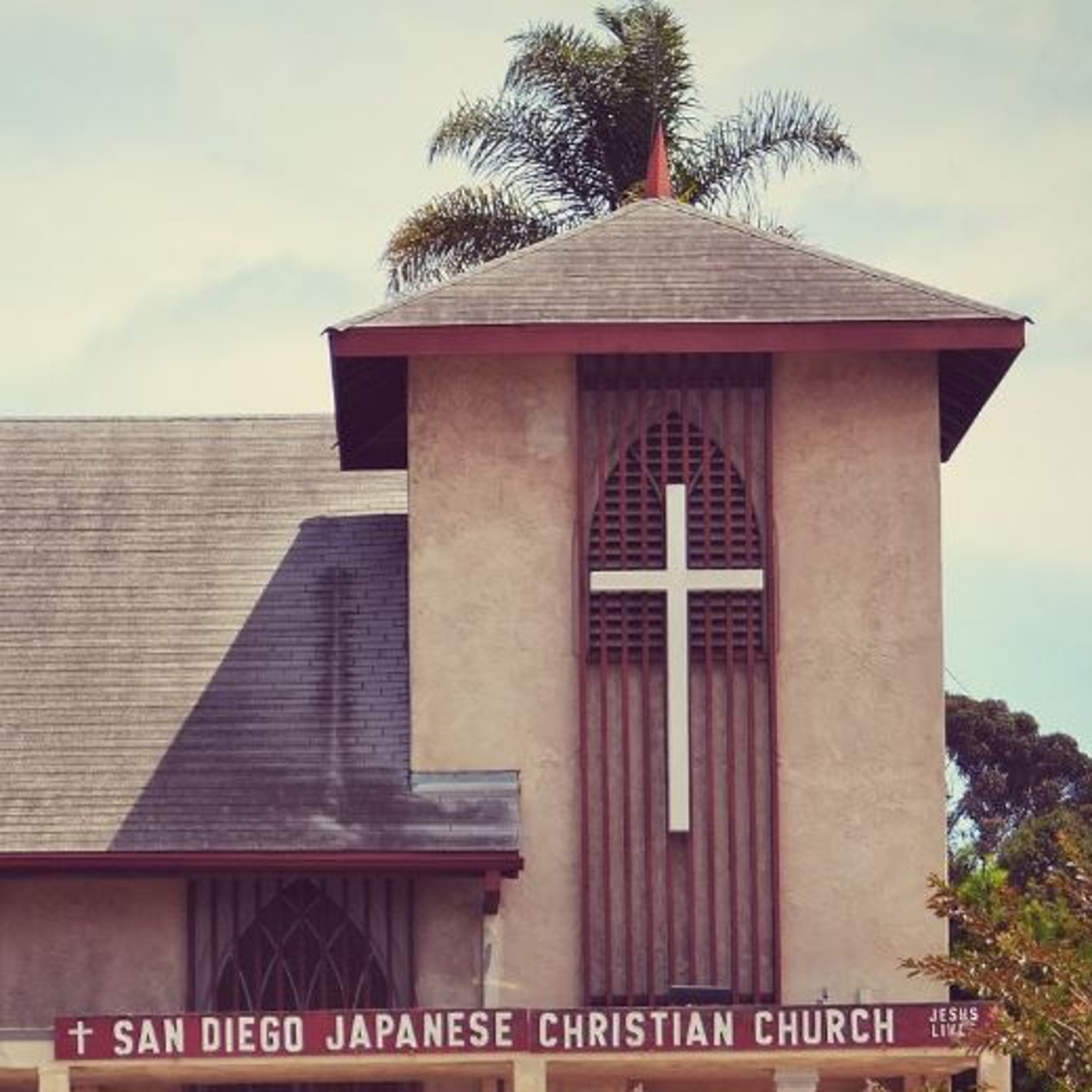Episodes
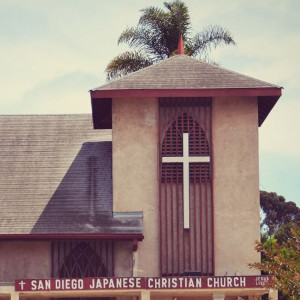
Sunday Apr 28, 2019
『復活、それから』大川道雄 師
Sunday Apr 28, 2019
Sunday Apr 28, 2019
「死んでも死なない命がありますように」という言葉が、昔は日本人の間に流行った言葉の一つでした。
イエスキリストは初穂として死を打ち破りよみがえられました。
キリストにあって人は永遠の命の中で生きることができるようになりました。驚くべき恵みです。
天地がひっくり返るような神の愛の実行です。
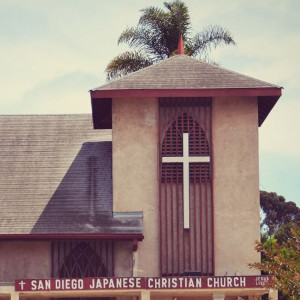
Sunday Apr 21, 2019
『イースターから見える神の心』大倉 信 師
Sunday Apr 21, 2019
Sunday Apr 21, 2019
最近、韓国企業が「次世代の5Gの携帯電話を世界で一番、最初に発売したのは我々だ」と名乗り出ました。そうしましたら「いいや、そうじゃない、アメリカが最初だ」とアメリカがクレームを出し、最後には韓国の大統領まで出てきて「いや、わが国が世界最初なのだ」と主張しました。人はいつも「一番最初である」ということにこだわるのです。
神の子キリストが死を打ち破り、空間を超越したお方として復活なさるのなら、イエス様は世界のどこにも姿をあらわすことができました。もし天に広報担当なる御使いがいたのならイエス・キリストの復活をどのように世の中に伝えるか戦略を練ったことでしょう。そして、考えたに違いありません。その第一報は誰に託したらよかろうかと。
その候補者を選ぶ時の選考の基準はきっとこうなることでしょう。このニュースが全世界に伝わるという目標を達成するために、大きな影響力を持っている人物を選ばなければならないと・・・。
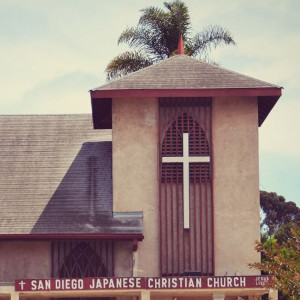
Sunday Apr 14, 2019
『この御恩を決して忘れてはならない 』大倉 信 師
Sunday Apr 14, 2019
Sunday Apr 14, 2019
十字架に磔にされるという痛みは到底、人間が耐えられる類の痛みではなく、実際にこの時のような痛みを表現する言葉が英語にはなかったために、Excruciatingという新しい単語が英語では作られたのです。これは極限の肉体の痛みを言い表す言葉で「耐え難い・極度の・猛烈な」という意味があります。この言葉の中には「十字架にかける」というCrucifyという言葉が含まれていることにお気づきでしょうか。
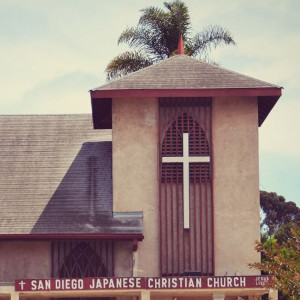
Sunday Apr 07, 2019
『現実的な投資の勧め 』大倉 信 師
Sunday Apr 07, 2019
Sunday Apr 07, 2019
ルカ2章には幼子イエスを連れてヨセフとマリアがエルサレムに宮詣でをする場面が記録されています。その時、通常ユダヤ人はこの宮詣でで子羊のような動物を捧げるのですが、彼らは山鳩一つがい、もしくは家鳩のひなを宮に捧げたと聖書は記録しています。なぜでしょうか?なぜなら彼らには子羊は買えなかったからです。
主にある皆さん、イエス様は家庭の経済的な理由で買えないものがあり、買うことを我慢しなければならない家庭に育ったのです。
このことはすなわち生きることの厳しさを知っているお方が、生きることの厳しさを知っている者達に語りかけているということを表しています。
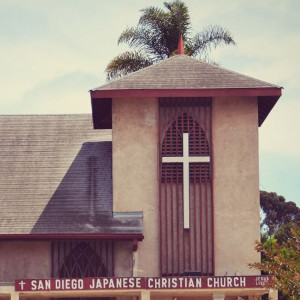
Sunday Mar 31, 2019
Sunday Mar 31, 2019
車のタイヤを替えたことがある方なら経験したことがあると思います。新しいタイヤを車につけた後、それから5000マイルほど走った後に車のローテーションを調節するからもう一度、持ってきなさいと言われます。
もって行くと車はそれぞれ4つのタイヤが等しく地面に触れて、バランスよく回っているかということが調べられるのです。そして、もしそのバランスが良くないということが分かれば、すぐさま、それぞれ4つのタイヤは調節されるのです。
なぜ、このようなことをするのか。この修正がなされなければタイヤの表面がアンバランスに磨り減ってしまうからです。そして、最悪の場合、事故につながることもあるからです。
このタイヤ・チェックにおいて「5000マイルを走ってみて」というのは大切なことを物語っています。新品のタイヤに交換した当初はいいのです。しかし、それがしばらく走行した後には、やはり少しづつ不具合がでてくるのです。その具合が一目瞭然で分かればいいのですが、見ただけでは分からず、それ故にそのままにしておくことによって、後で大きなツケが回ってくるのです。